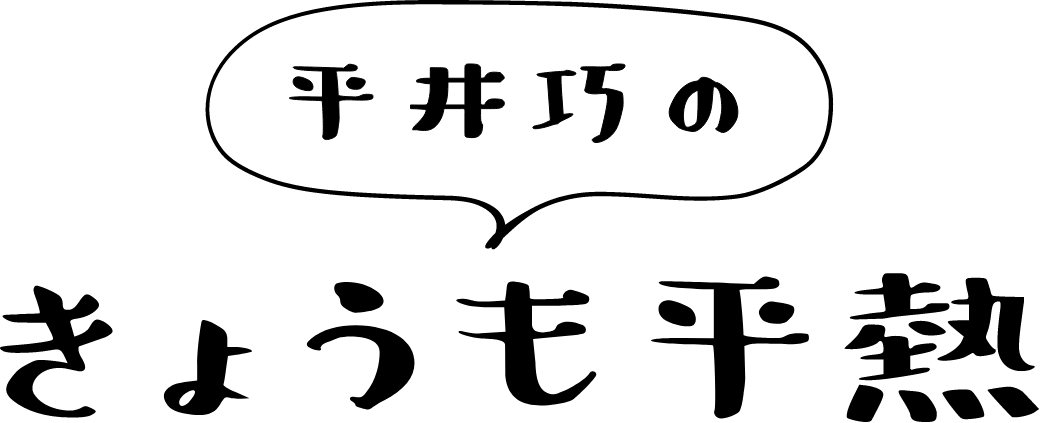
Shokuyokuマガジン編集長の平井巧が書く平熱エッセイ。
食のことも、食以外のことも、いろいろ思ったことを書いていきます。
ここ5、6年の話だけど、講師として授業をもつ小中学校や高校、大学で若者と話をしていて、「将来は野菜作りをしたいから農家さんの話を聞きたい」とか、「フードロスの現状を何とかしたいからボランティア活動している」とか、具体的な食への関心を持つ若者は思っていた以上にいるぞと感じている。
社会に出た人の中には「食を教養として学びたい」という人が一定数いて、例えばフードロスの講演やイベントをさせてもらっても、参加する人は相変わらず多くて、するどい質問があったり終わった後にはたくさんの感想をもらえる。
「食を教養として学びたい」と思う人が、老若男女問わず増えてきているのではないか。畑中三応子さんが著書『ファッションフード、あります。』の中で書かれているように、食の大量生産・大量消費全盛の1960年代に、空腹を満たし栄養を摂取するという「食」本来の機能から解放され、情報化社会にさしかかった1970年あたりから、食をレジャー化する傾向が加速した。そのころから流行の洋服や音楽、マンガなどのポップカルチャーと同じ次元で食が消費されるようになった。これを畑中さんは「ファッションフード」と呼んでいる。
ここからは僕の仮説だけど、日本ではファッションフードとして食が情報消費されてきて、今ほど食と環境問題が直結しているとも思われていなかったから、「食」は教養として勉強するようなことではなく、消費財としてだけ見られることが強かったのではないか。ところがここにきて、「学びたい」と思う人たちが増えてきたのはなぜだろう。社会人としての文化的な広い知識を手に入れたいからなのだろうか。それもあるだろう。でも食について知りたいと思う人が増えてきたのは、生き物の本能的なものではないかと思っている。
そもそも人間は、その人類史において食料をどうやって手に入れて、保管して、料理して、口にして、それをいかに安全に継続させていくか、ということをずっと考え続けてきたわけだ。自分の生命を保つために、そして「ヒト」という哺乳類を次代に繋いでいくために。食について考え続けることは、ヒトが興ってから今まで本質は変わっていないのだ。人間にとって一番重要な問いは、「さて、どうやって食べよう」なのかもしれない。
食が環境問題に直結していることがわかってきてから、「どうやって食べよう」がより複雑化している。「どうやって食べよう」に答えなんてないし、答えがないということは、時々の状況によって最適な答えが変わっていくということだ。だからこそ人は食について学んで、自分にとっての最適解が見つかることを期待する。どうやら現代人は知らないだれかに食べ方を決められることに慣れすぎてしまった。自分で食べ方を選ぶことをしないと、生きる力がどんどん弱まっていくんじゃないだろうか。
昨年4月に開校した食の学び舎「フードスコーレ」では、生徒のみなさんと一緒に食にまつわる色んなことを学び合っている。フードスコーレの中で学び話題になったことは、日々の中で食と向き合う一助となっている。
たとえばスーパーの牛乳売場で「中洞牧場」の牧場主である中洞正さんの言っていた「日本人は牛乳を飲む習慣がなかった」という言葉を思い出したり。野菜売場に行けば、「やさいバス」の梅林泰彦さんが話してくれた「野菜はどうやって手元に届いているのか」が頭をよぎる。
講義の中で新しい知識を得て、他の人の意見も聞いて、自分の価値観を醸成しながら行動に移してみる。その感想をまた共有して、他の人にも影響を与える。食に関する問題は、解が「正と誤」のようにはっきりと別れているのではなく、解の段階的な濃淡の推移がある。100人いれば100通りの解があるのだ。
フードスコーレでは、自分の価値観を言える空気感がある。若い人が真逆の考えをもつ年配の人に対しても平気で意見を言える。言われた方もそれを許容する。そして互いに影響を与え合って変化も起きる。
何も考えないで過ごすのはある意味ラクなことだ。世の中にあることをすべて把握して、さまざまな問題についても考えて関わっていくことは無理だ。でもその中で「食」に関することは、人間活動する上で必要なことでもあるわけだから、「食を教養として学びたい」という人が周りに増えはじめてきたことはについては大歓迎だ。
2021年10月12日 平井巧